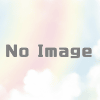香典袋の表書きの書き方
香典袋は薄墨で書く

香典袋の表書きの文字は、薄墨の筆で書くことが常識とされています。
これは涙で墨が滲んで薄くなるということを表しています。
水引の上半分、中央に用途を書きます。
用途は宗教や儀式の意味によって異なります。(下記参照)
仏式香典袋には「御霊前」等
仏式では「御霊前」「御香典」「御香料」などと書きます。
浄土真宗では、死後すぐに、魂は仏となると考えられ、霊の存在は認めてないということで「御仏前」を用います。
白無地、または、蓮(はす)の絵柄のついた不祝儀袋に、白黒または双銀の結び切りの水引をかけます。
四十九日法要以降は「御仏前」または「御供物料」と表書きをし、黄白の水引をかけます。
神式香典袋には「御玉串料」等
神式では「御玉串料」「御榊料」「御神前料」「御霊前」などと書きます。
白無地の金包みに、双銀または双白の結び切りの水引をかけます。
キリスト教式香典袋には「御花料」等
キリスト教式の場合は宗派により「御花料」「献花料」「御ミサ料」などと書きます。
白無地の封筒、あるいは白百合・十字架などが印刷された市販の封筒を使い、水引はかけません。
香典袋の下半分には氏名を
水引の下側中央に、香典をたむける方の、名前をフルネームで書きます。
連名で香典を出す場合には、右から代表格の人や、年長者など目上の人となるように記入します。
上下関係が無い場合には五十音順でもよいでしょう。
4人以上の連名で出す場合は、中心に代表者の姓名だけを記し、左側にやや小さく「他一同」と記します。または代表者を記さずに「○○一同」とだけ記すこともできます。
どちらの場合も別紙に、一同の姓名、住所、そして各々の金額を記して同封します。