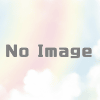初盆の香典とお供え
初盆とは

一年に一度、死者の霊が家に戻ってくるといわれるのがお盆です。また、人が亡くなった後、初めて迎えるお盆のことを、初盆または新盆といいます。
初盆は、故人が仏になって初めて里帰りすると考えられ、とりわけ死者に対する思いいれの強い日であります。初盆を迎える家では精霊棚を作り、迎え火をたいてお迎えをします。
親族や親しい方々を招いて、僧侶にお経をあげてもらい、盛大に供養を営むこともあります。
このときには、決まった供物のほかに、故人の好物などを供えます。
お経がすんだら、茶菓子や精進料理などでもてなし、お布施を渡します。お布施の金額は大体三万円から五万円が一般的です。
四十九日の忌明前にお盆を迎える場合の新盆は、翌年になります。
お盆での香典・供え物の様式
お香典、お供え物の贈答様式は次のようになります。
・お香典の水引は、黒白・黒白銀・黄白で、5本か7本のもの、または双銀の7本か10本のもので、結切りか鮑結びのものを用います。
表書きは「御霊前」「御仏前」「御供物料」と書きます。
・のし袋の水引は藍銀で蓮絵入りがないもの、または黄銀で5本か7本のもの、結切りか鮑結びのものを用います。
表書きは「御霊前」「御仏前」「御供物料」と書きます。あるいは「御供」「御供物」でも構いません。
一般的にはお返しの必要ありませんが、地域により慣習があるようです。また、近所の方など「御供物」などを頂いた場合には「志」と表書きした引き物を渡します。
引き物の品物は、香典返しでよく使われるお茶、タオルセット、ハンカチなどが多いようです、近年は慣習にとらわれず、お返しの品もいろいろと選べるようになっています。