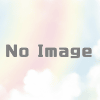香典は昔米であった
◆香典の由来

香典とは仏事においては香を献ずることから、香料として、故人にお供えする金銭や物品のことをいいます。
現在では金銭を包み香典としますが、かつては金銭よりも葬儀に用いる食品、なかでも、米を供えることが一般的でした。
近親者は関係によって香典の金額が増えますが、これは米や食品でも同じでした。特に米の場合、地域によって、俵で供える慣習がみられたのです。
また別の地域では、故人の子供はそれぞれ現金のほか、米二俵、兄弟などは米を一俵などと、大量の米を供えたのです。そして、俵を祭壇の脇などに飾って喪家の偉容を誇ることもありました。
◆昔は葬儀に多くの人手を要した
昔、葬儀では近親者は死の忌みのため籠もっているもので、地域の人々が葬具を準備し、火葬や土葬を行うなど役割を担いました。
多くの人手を必要としたため、食品の調達は重要でした。
香典として供えられた米や現金が葬儀を支え、喪家に蓄えがなくとも、葬儀を出すことが出来たのでした。
◆香典返しの簡略化
供えられた香典は、相手の不幸の際に同じように返すことが期待されました。そのため代々香典帳は保存され、後の参考にされたものです。
香典に対するお礼は相手への香典によってされたため、香典返しは行われていませんでした。しかし、このような風習は時代とともに簡略化されていました。
また相手の葬儀の際に、相応の香典を出すことが難しい場合や、香典をもらったままになり借りを作ってしまうということもありました。
そこで、将来に借りを残さないよう対応されたものが、香典返しだと考えられます。ただし、全額分を返しては好意を無にするということから、半返しという方法が一般的になったのでしょう。